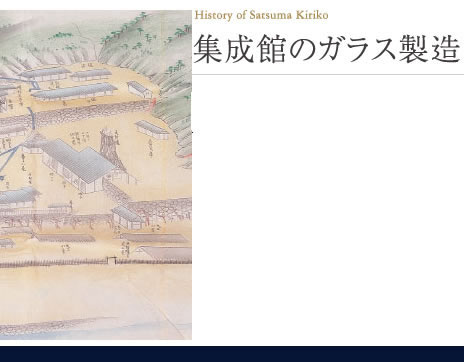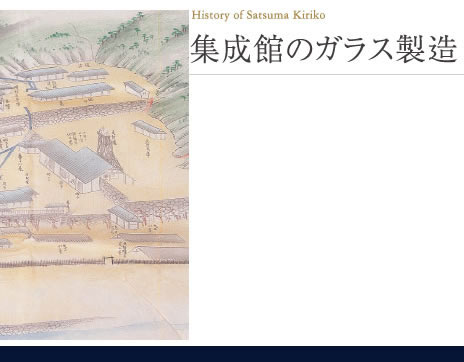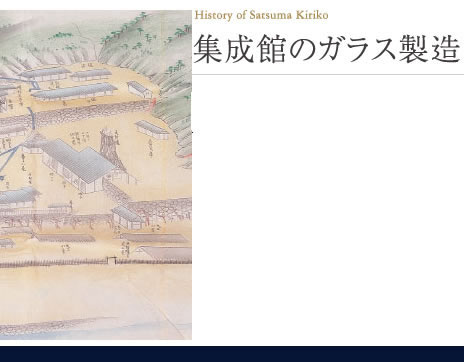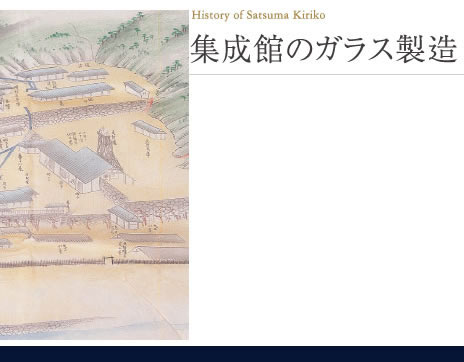19世紀イギリス、フランスなどの西欧列強が植民地を求めてアジアに進出し、日本にも欧米諸国開国、通商を強行に求めていた時代。諸藩が軍備の近代化に力を注ぐなか、斉彬は富国強兵を掲げ、日本を強く豊かな国にしようとしました。そんな中、薩摩切子は海外交易品として開発されたのです。源流をイギリス、ボヘミア、中国に求めながらそれを凌駕し、「ぼかし」などの日本的な特徴は斉彬の海外進出という壮大な夢に裏付けされた意匠だったのです。
19世紀イギリス、フランスなどの西欧列強が植民地を求めてアジアに進出し、日本にも欧米諸国開国、通商を強行に求めていた時代。諸藩が軍備の近代化に力を注ぐなか、斉彬は富国強兵を掲げ、日本を強く豊かな国にしようとしました。そんな中、薩摩切子は海外交易品として開発されたのです。源流をイギリス、ボヘミア、中国に求めながらそれを凌駕し、「ぼかし」などの日本的な特徴は斉彬の海外進出という壮大な夢に裏付けされた意匠だったのです。
 島津家28代 藩主島津斉彬は、日本を強く豊かな国にするため、集成館事業という大規模な近代化事業を推進しました。鹿児島城下郊外の磯に築いた工場群「集成館」を中核に、製鉄・造船・造砲・紡績・印刷・製薬など様々な分野の事業を興しました。硝子工場では最盛期には百名を超える職工が働いており、切子の他瓶類や板ガラスなど様々な種類の硝子器を製造していました。
島津家28代 藩主島津斉彬は、日本を強く豊かな国にするため、集成館事業という大規模な近代化事業を推進しました。鹿児島城下郊外の磯に築いた工場群「集成館」を中核に、製鉄・造船・造砲・紡績・印刷・製薬など様々な分野の事業を興しました。硝子工場では最盛期には百名を超える職工が働いており、切子の他瓶類や板ガラスなど様々な種類の硝子器を製造していました。
 薩摩藩におけるガラスの製造は1846年島津家27代島津斉興の代に始まり、江戸から当時硝子師として著名であった四本亀次郎を招聘しガラス瓶などを製造させました。そして1851年、28代島津斉彬が藩主になると飛躍的な発展を遂げることとなり、花園跡製煉所(鹿児島城内)において着色ガラスの研究がなされ、紅・藍・紫・緑等の発色に成功しました。中でも、日本で初めて発色に成功した紅色は「薩摩の紅ガラス」として当時都鄙を問わず称賛されたと言われます。
薩摩藩におけるガラスの製造は1846年島津家27代島津斉興の代に始まり、江戸から当時硝子師として著名であった四本亀次郎を招聘しガラス瓶などを製造させました。そして1851年、28代島津斉彬が藩主になると飛躍的な発展を遂げることとなり、花園跡製煉所(鹿児島城内)において着色ガラスの研究がなされ、紅・藍・紫・緑等の発色に成功しました。中でも、日本で初めて発色に成功した紅色は「薩摩の紅ガラス」として当時都鄙を問わず称賛されたと言われます。
 藩主就任から僅か7年後の1858年、斉彬の急逝による財政整理のため集成館事業は縮小、さらには1863年の薩英戦争で工場は焼失して大打撃を受けました。その後、ガラス製造の再開や明治初期までガラス工場が存続していたと考えられる記述も残されていますが、確かなことは分かっておらず、いずれにしても明治10年(1877年)の西南戦争前後に薩摩切子の技術は跡絶えてしまいました。薩摩切子が今日まで存続して、その技術と伝統を培っていたとしたら、日本のガラス工芸に及ぼした影響は計り知れないものがあったことでしょう。
藩主就任から僅か7年後の1858年、斉彬の急逝による財政整理のため集成館事業は縮小、さらには1863年の薩英戦争で工場は焼失して大打撃を受けました。その後、ガラス製造の再開や明治初期までガラス工場が存続していたと考えられる記述も残されていますが、確かなことは分かっておらず、いずれにしても明治10年(1877年)の西南戦争前後に薩摩切子の技術は跡絶えてしまいました。薩摩切子が今日まで存続して、その技術と伝統を培っていたとしたら、日本のガラス工芸に及ぼした影響は計り知れないものがあったことでしょう。
 幻となってから約100年後、斉彬が築いた世界に誇るガラス工芸の歴史を再興させたいとの熱い思いから1985年にゆかりの地、鹿児島市磯に薩摩ガラス工芸が設立されました。当初、紅・藍・紫・緑の4色の薩摩切子を復元。そして文献には生産の記述がありながら、現存するものが見つかっていなかった幻の金赤と黄色をの再現に成功。2005年には斉彬ゆかりの新色島津紫を加えました。更に深い色彩から透明へと移り行く美しいグラデーションと繊細なカット技術を駆使し新しいタイプの薩摩切子の製造にも積極的に取り組んでいます。
幻となってから約100年後、斉彬が築いた世界に誇るガラス工芸の歴史を再興させたいとの熱い思いから1985年にゆかりの地、鹿児島市磯に薩摩ガラス工芸が設立されました。当初、紅・藍・紫・緑の4色の薩摩切子を復元。そして文献には生産の記述がありながら、現存するものが見つかっていなかった幻の金赤と黄色をの再現に成功。2005年には斉彬ゆかりの新色島津紫を加えました。更に深い色彩から透明へと移り行く美しいグラデーションと繊細なカット技術を駆使し新しいタイプの薩摩切子の製造にも積極的に取り組んでいます。
 まずは島津家に残されている関連資料を読み進め、尚古集成館に収蔵されている薩摩切子を実測致しました。実測は細部にわたっての情報を入手するための大変重要な作業でしたが、多くのものはたった1枚の写真のみを基に復元することを余儀なくされました。様々な調査記録を参考にその特徴や使用工具の形状などを推察し加工設備の準備に取り掛かり、1986年3月には本工場が完成し色の研究も始まりました。「薩摩の紅硝子」と珍重された紅色の発色を安定させ、納得のいく色になるまでさらに数年の歳月がかかりました。
まずは島津家に残されている関連資料を読み進め、尚古集成館に収蔵されている薩摩切子を実測致しました。実測は細部にわたっての情報を入手するための大変重要な作業でしたが、多くのものはたった1枚の写真のみを基に復元することを余儀なくされました。様々な調査記録を参考にその特徴や使用工具の形状などを推察し加工設備の準備に取り掛かり、1986年3月には本工場が完成し色の研究も始まりました。「薩摩の紅硝子」と珍重された紅色の発色を安定させ、納得のいく色になるまでさらに数年の歳月がかかりました。